| |
”燃焼”は,自動車や航空機,ロケット,火力発電所など,我々の生活のいたるところで使用されていますが,主に化石燃料を用いることから,燃焼資源の枯渇の問題があります.また,燃料として一般に用いられる天然ガス,ガソリン,軽油,重油を燃焼させると二酸化炭素が排出されますので,地球温暖化の問題もあります.これらの問題を解決するには,燃焼器の低燃費化・排気浄化が必要であり,次世代に豊かで住みよい地球環境を引継ぐためにも,燃焼技術に関わる研究開発が急がれています.当研究室では,燃焼現象に関わる基礎研究を中心に活動しています.
このページでは,現在行っている研究について紹介します.
|
|
| |
燃料の濃度変動に対する予混合火炎の応答特性に関する研究
Response Characteristics of Premixed Flame to Fuel Concentration Oscillation |
|
| |
|
|
| |
ガソリンを直接燃焼室に噴射する,直噴ガソリンエンジン内において,燃料濃度の分布は不均質であることから,火炎は非一様な燃料濃度分布を有する混合気中を燃え広がることになります.ガスタービン燃焼器においても,燃料濃度の振動による振動燃焼が観察されています.この燃料濃度の不均一性を燃料濃度の正弦波振動でモデル化することによって,燃料濃度の正弦波振動が火炎の応答に及ぼす影響を調査しています. |
|
| |
|
|
| |
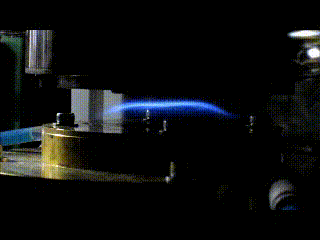 |
|
| |
Response of CH4/air flame to fuel concentration oscillation |
|
| |
|
|
| |
この実験では,バーナから上に向かってメタンと空気の混合気を噴出させています.この混合気をバーナの上部に設置している壁に衝突させて着火すると,動画に見られる円盤形状の火炎が形成されます.ここで,バーナ出口における混合気の吹出し速度を一定とし,燃料濃度だけを正弦波的に変化させると,火炎は上下に移動します.この研究において,濃度変動だけを与えているにも関わらず,火炎が移動することによって混合気の流れを変化させることなどが世界で初めて観察されました.流れの変化は燃料や酸素の輸送にも影響を与えるため,より詳細な調査を進めています.
|
|
| |
|
|
| |
燃料ノズルの形状が拡散火炎のすす排出に及ぼす影響
Influence of fuel nozzle geometries on soot emission from diffusion flame |
|
| |
|
|
| |
ボイラーなどの燃焼器では,拡散燃焼(非予混合燃焼)が多く用いられます.拡散火炎は,燃焼器の構造を簡単にできる一方,すすが排出しやすいという欠点があります.当研究室では過去に,燃料流を能動的に制御することによって拡散火炎からのすす排出を抑制できるのではとのアイデアに基づき実験を行ったところ,逆にすす排出が促進される結果を得てしまいました.そこで, 燃料流を受動的に制御するといった,逆転の発想で,この研究テーマが生まれました.実際に,断面形状が円形,正方形,三角形の燃料ノズルを製作し,実験を行ったところ,燃料流量がある値を超えると,円形以外のノズルにおいてすす排出が抑制されることが明らかとなりました. |
|
| |
|
|
| |

Diffusion Flame Formed on Square Nozzle |
左の写真は,正方形の燃料ノズル上に形成される拡散火炎の様子を示しています.燃料ノズル近傍において,火炎の輪郭は正方形に近い形状ですが,上方に行くにつれて火炎の輪郭は円形に変化しているように見えます.しかし,火炎の構造(例えば,すすの濃度分布)を調べてみると,火炎の基部だけではなく,火炎の先端にも特徴的な構造が見られることがわかってきました.現在,流れ場と火炎構造を詳細に調査するため,高速度ビデオカメラや高出力レーザーを用いて実験しています. |
|
| |
|
|
|